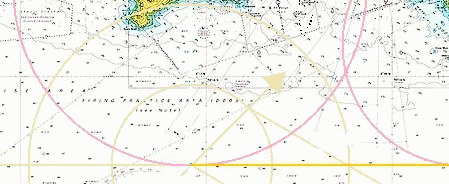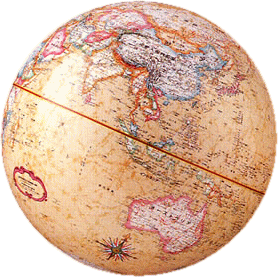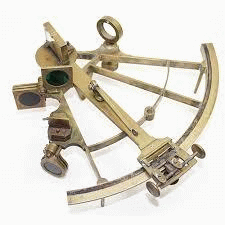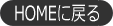| | |
|
 船・海用語集
|
|
Law and Term
 海事関連法規の照会サービスと用語集です。 |
|
|
|
|
船舶免許を持っている人なら読んでおくべき海事関連法規の照会サービスと、絶対知っておかなければならない用語やふだんはあまり耳にしないけど気になる用語などを集めてみました。
|
|
当舵(あてかじ Steady) |
|
|
目標針路を超えて回頭しそうなときにそれを防ぐための操船のこと。当舵の大きさは、その船の舵効きや、喫水の状態によって変わるので、その状況に応じて調整します。
|
|
|
アンカー(あんかー Anchor) |
|
|
錨(いかり)、碇(いかり)とも言います。船の設備のひとつで船を水上の一定範囲に留めておくために、鎖やロープを付けて水底へ沈めて使うもの。
使用例:投錨(とうびょう)する。アンカーを打つ。
爪などが底質に刺さる事で抵抗力(把駐力)を生む物をアンカー、それ自身の重さによって抵抗力を生むものをシンカーと分類しています。アンカーとシンカーでは構造や使用方法が異なり、アンカー自体も使用される場所や船舶によって大きさ種類・使用方法が異なります。
船や航海を連想させるものとして、シンボル的に用いられることも多くあります。
Anchor(アンカー)の語源は、Ank(曲がった)に由来しており、Ankle(アンクル、かかと)や Angle(アングル、角度)なども同源の単語です。 またアラスカの港湾都市であるアンカレッジは、投錨地(anchorage)に由来しています。
|
|
|
右舷(うげん Starboard side) |
|
|
船舶の進行方向に向かって(船尾から船首方向に見て)船の右側のこと。
古い時代の船は、右舷の船尾に取り付けられた舵板(STEERING BOARD)で、コントロールする仕組みになっていました。(「STEERING BOARD」が後に、「STARBOARD」に変化したと言われています。)
船が港に到着するとき、右舷には舵板があるため船は左舷から接岸して、人の乗り降りや荷物の積み卸しをするのが慣習となりました。それで、左舷を「ポート・サイド(港側)」と呼ぶのです。
ちなみに飛行機の機体を交換することをシップチェンジと呼びますが、ボーディングブリッジなどをはじめ、客室を「キャビン」、乗員を「クルー」、機長を「キャプテン」と呼ぶことなど、現在の航空機はほとんどが船の慣習に基づいたものです。
そういえば制服のイメージもどことなく似た雰囲気ですね。
|
|
|
運転不自由船(うんてんふじゆうせん) |
|
|
エンジンが故障し自らは動くことのできない船舶のこと。ほかにも、舵が故障した船や風がないので動けない帆船などがあげられます。このように、他の船を避けることができない船舶のことを指します。
|
|
|
追越船(おいこしせん) |
|
|
船舶の正横後22度30分を超える後方の位置から、その船舶を追い越す船舶を「追越し船」と呼び、追越し船は追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならないと定められています。
|
|
|
面舵(おもかじ Starboard) |
|
|
右に舵をとり、船を右旋回させること。反対語は取舵(とりかじ)。
|
|
|
海上交通安全法(かいじょうこうつうあんぜんほう) |
|
|
船舶交通がふくそうする海域において、特別な交通方法を定めたり、危険を防止するための規制を行うことにより、船舶交通の安全を図るための法律のこと。現在では、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海に適用されます。
海事法規照会サービス参照のこと。
|
|
|
海上衝突予防法(かいじょうしょうとつよぼうほう) |
|
|
海の道路交通法とも言われ、海上における船舶の衝突を避けるための航法、船舶が表示すべき灯火・形象物および実施すべき信号などを定めた、船舶の運航上もっとも重要かつ基本的な法律のこと。
海事法規照会サービス参照のこと。
|
|
|
海図(かいず Chart) |
|
|
海洋に港湾などの形状、底質、海流、水深、暗礁その他の障害物、島沿岸の地形、地物、航路標識などを表示した地図で、航海を行なう上で必要です。
海図には、海上保安庁刊行のものと、日本水路協会刊行のものがあります。
|
|
|
海里(かいり Nautical mile) |
|
|
海里(マイル、mile)
海里は距離を表す単位です。
船では距離を表すのに、ほとんどの場合海里を使いメートルを使うことは極めてまれです。
1 海里とは緯度1分(ふん)を表す長さです。
船の位置を表すには緯度と経度を使用しますので、緯度1分という単位を使うと航海に非常に便利な訳です。南北に 60海里移動すると緯度1度移動したことになります。
このように、緯度に直ぐに結びつけられるため、非常に便利な値なのです。
それでは、1海里という単位を私たちが最も親しんでいる長さの単位メートルに直してみましょう。
赤道から極までは90度、5400(=90×60)分です。
また、この距離は 10,001,960 m(理科年表より)ですので、これを5400で割ってやれば、1海里(M)をメートル(m)で表すことができます。
赤道から極までの海里
計算してみると、次のようになります。
1 M = 10001960m / 5400 = 1852 m
ちょっと中途半端で覚えにくい値ですけれど、航海する上で最も重要な値の一つです。
余談ですが、メートルという単位について。
赤道から極までの距離を1/10,000,000(千万分の1)したものを 1 m としました。
赤道から極までの弧の距離(10,001,960m)を千万分の1すると、1 m になります。
また、マイルですが陸マイルと海マイルがあります。
陸マイルは世間一般的にマイルと言っている物であり、アメリカの自動車なんかは速度表示がマイル/時間(日本はkm/時間)で表示します。
この場合1マイル=1.609kmなので、200×1.609=321.8kmとなります。
海マイルは海里(かいり)と言われる物で航空業界や海運業界といった飛行機、船の世界で使われます。
飛行機は船舶からの引用が多く、船長・機長はキャプテンと呼ぶし、船体・機体はシップと呼ぶし、歓迎はなぜか港の消防艇からの放水を模して空港でも消防車による放水アーチです、
飛行機の距離計算もこの海マイル 海里(かいり)で計測されます。
この場合1マイル=1.852kmなので、200×1.852=370.4kmとなります。
ちなみに1海里/時間は、1knot(ノット)といい、飛行機、船の速度の単位に使われます。
|
|
|
舵(かじ Rudder) |
|
|
舵とは、主に船舶の進行方向を自在に定めるための設備装置、およびその操作部を指します。
水中の板そのものを舵と呼ぶと同時に、船の操縦者である「操舵手」が操作する輪状の操作部も舵、または「操舵輪」と呼ばれます。また、操舵手が舵を操作することを「操舵(そうだ)」と呼びます。
船舶にならい、航空機や自動車などでも進行方向を変える操作を「操舵」と呼んだり、その機構を同じく「舵」と呼ぶ場合があります。
船舶の舵の多くが水中の板によって水流の流れを変えることで進行方向を変化・調節する仕組みであり、その板を舵と呼びます。
大型船では船体後部の船底、小型船では船尾に取り付けられ、船体中心軸に対する角度を左右に変えることができます。
スクリューを持つ船舶では多くがスクリュー直後に位置し、前進回転中のスクリューが生み出す強い水流の向きを右、又は左方向へと変えることで船体の向きを変えます。向きを変えられた船体はやがて自らの船首船尾軸方向へと針路を変え、これが「転針」と言われます。
このような船では、スクリューが停止していれば舵の効果は下がり、逆回転中は舵効きが極度に悪くなります。ヨットなどのスクリューを持たない船舶では、船体が進むことで生じる水流を受け、船体へ反動を伝えることで船舶の向きを変えます。
|
|
|
旗国(きこく Flag state) |
|
|
船舶が登録されている国のこと。旗国は自国に登録された船舶の保護と、安全な運航の確保についての権限を行使しなければなりません。
旗国の権限は、特に何れの国も主権の行使ができない公海の秩序維持に及びます。
つまり、登録船舶を通じて間接的に国際的な秩序の形成を担っていることになります。
|
|
|
喫水(きっすい Draft) |
|
|
船が水に浮いている状態で水中部分の船底から水面までの垂直方向の長さのこと。通常言われる深さのことです。大きな船では20メートルを超えることがあります。船の重さを計るときや水先料の算出にも使われます。
|
|
|
キール(きーる Keel) |
|
|
竜骨(りゅうこつ)。船舶の構造材のひとつで、船底を船首から船尾にかけて通すように配置された構造材のこと。
また英語でkeel キールと言えば、船舶の下に配置された水中構造体を指すこともある。
|
|
|
係留(けいりゅう Mooring) |
|
|
いつでも運航できる状態で、船を一時的につなぎ止めておくこと。
|
|
|
コンパス(こんぱす Compass) |
|
|
コンパスとは、地球の磁気(地磁気)と磁石の性質を利用して地球上での基準方位(子午線)を知る装置のこと。
|
|
|
左舷(さげん Port side) |
|
|
船舶の進行方向に向かって(船尾から船首方向に見て)船の左側のこと。
右舷の項参照のこと。
|
|
|
三角波(さんかくなみ Pyramidal wave) |
|
|
三角波とは、進む方向が異なる二つ以上の波が重なり合ってできる、三角状の波高の高い波のこと。波の峰がとがっていて三角に見えることからそのように呼ばれます。
例えば、暴風の中心が通る水上などに起こる。暴風域のいたるところで波が発生しているため、それらの波が全て様々な角度で重なりあうため発生する。入射波と反射波が重なりあうような場所、例えば絶壁や防波堤などの近くでも発生することがあります。また、潮流の向きと風の向きが反対の場合にも生じます。
このようなところでの航海は大変危険を伴うために船乗りからは大変恐れられている波です。沈没の危険もあり経験豊富な船乗りでも近付かない波です。万が一、入ってしまった場合は速やかにその海域から脱出する措置を講ずることです。
|
|
|
潮汐(ちょうせき tide) |
|
|
潮汐(ちょうせき、英語: tide)は、主に他の天体の影響(潮汐力という)により、天体の表面などが上下する現象です。
地球の海面の潮汐である海洋潮汐・海面潮汐(満潮・干潮)が広く知られていますが、湖沼でも琵琶湖、霞ヶ浦程度の大きさがあれば起こります。
「しお」ともいいます。漢字では潮と書きますが、本来は「潮」は朝のしお、「汐」は夕方のしおの意味です。
海(や大気)のように天体の表面が流体で蔽われている場合、潮汐にともない、表面が下がるところから上がるところへ流体が寄せ集められるために流体の流れ(水平動)が生まれます。これを潮汐流(「潮流」とも)といいます。潮汐という言葉でこれを指すこともあります。
海面は潮汐力以外の要因でも上下し、気圧差や風によるものを気象潮といいます。代表的な気象潮は高潮(たかしお)です。気象潮と区別するため、潮汐力による潮汐を天体潮・天文潮ということがあります。
潮汐力とは、少し話が難しくなりますが、物体に働く重力場が一定でなく、物体表面あるいは内部の場所ごとに異なっているために起こります。ある物体が別の物体から重力の作用を受ける時、その重力加速度は、重力源となる物体に近い側と遠い側とで大きく異なります。これによって、重力を受ける物体は体積を変えずに形を歪めようとします。球形の物体が潮汐力を受けると、重力源に近い側と遠い側の2ヶ所が膨らんだ楕円体に変形しようとするのです。
なお、潮汐表は満潮時刻・干潮時刻などを表にまとめたものです。
航海の用に供する公式の潮汐の推算は、航海等における混乱を防ぐため、各国の水路機関が責任を持って行うことになっており、海上保安庁海洋情報部で毎年刊行している「 潮汐表」が公式の潮汐推算値です。
|
|
|
取舵(とりかじ Porting) |
|
|
左に舵をとり、船を左旋回させること。反対語は面舵(おもかじ)。
|
|
|
灯台(とうだい Lighthouse) |
|
|
灯台(とうだい)は、岬の先端や港内に設置され、その外観や灯光により船舶の航行目標となる施設のこと。航路標識のうち光波標識の一種です。
塔状の建造物で、最上部には遠方からでも識別可能な強力な光源が設置されています。夜間には光源が明滅し、航行する船舶が場所を識別する目印となります。
我が国おいては総括的には海上保安庁交通部(旧灯台部)が所管し、個々の設置・維持・管理等を各管区海上保安本部所轄下の海上保安部が行っています。また灯台は多くの国においても、いわゆるコースト・ガード(沿岸警備隊)あるいは港湾行政当局の管理下にあります。
灯台表(海上保安庁発行)や海図には各灯台の灯質が記号で表記されています。代表的な灯質としては以下のものがあります。
・不動光 (F, fixed): 一定の光度を常時維持している
・明暗光 (Oc, occulting): 一定の光を放ち、明間が暗間より長い
・閃光 (Fl, flashing): 約1秒程度の閃光を放つ(長閃光、急閃光がある)
・互光 (Al, alternating): 異色の光を交互に放つ
・モールス符号光 (Mo)
|
|
|
登録教習所(とうろくきょうしゅうじょ) |
|
|
国土交通省に登録認可を受けた教習所のことです。学科と実技の課程を修了することにより国家試験免除で小型船舶免許を取得することが認可されています。ビーエルエス東北はこの登録教習所です。
|
|
|
内水(ないすい Internal waters) |
|
|
海洋の区分の一つであり、通例、領海の幅を定めるための基線(低潮線)から陸地側の海域を示します。内水を領有する国家は内水に対してもその領土と同様の主権を有し、外国船舶の進入の是非は領有国の裁量に任されています。内水の定め方については国連海洋法条約に規定があります。
また、領海とは国家の海岸に沿う基線より外海へ12マイルを越えない範囲で定められた帯状の海域です。上空、海底及びその下を含めた領海は、沿岸国の主権に服する国家領域の一部です。
なお、排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき Exclusive Economic Zone 略称EEZ)とは、国連海洋法条約に基づいて設定される、天然資源及び自然エネルギーに関する「主権的権利」、並びに人工島・施設の設置、環境保護・保全、海洋科学調査に関する「管轄権」がおよぶ水域のことを指します。
|
|
|
ノット(のっと Knot) |
|
|
速度を表す単位。1ノットは、1時間に1海里進む速さです。1海里(国際海里) = 1,852メートルなので、1ノットは1,852メートル毎時となります。
1ノット=1.852 km/h
20ノット=20×1.852 km/h=37.04 km/h
20ノットの場合、時速37.04キロメートルとなります。
|
|
|
排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき Exclusive Economic Zone) |
|
|
排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき Exclusive Economic Zone 略称EEZ)とは、国連海洋法条約に基づいて設定される、天然資源及び自然エネルギーに関する「主権的権利」、並びに人工島・施設の設置、環境保護・保全、海洋科学調査に関する「管轄権」がおよぶ水域のことを指します。
国連海洋法条約では、沿岸国は自国の基線 (海)から200海里(370.4km<1海里=1,852m>)の範囲内に排他的経済水域を設定することができるとしています。
設定水域の海上、海中、海底及び海底下に存在する水産・鉱物資源並びに海水、海流、海風から得られる自然エネルギーに対して、探査、開発、保全及び管理を行う排他的な権利(他国から侵害されない独占的に行使できる権利)を有することが明記されています。
排他的経済水域に存在する鉱物資源は埋蔵している段階では沿岸国には所有権は存在せず、採掘して陸上・海上施設・船舶に引き上げられた段階でその権利が発生します。また水産物も水揚げされて初めて所有権が発生します。自然エネルギーに対しても、例えば電力に変換されてはじめて物権が発生します。
批准沿岸国は天然資源及び自然エネルギーに対する行為に関してのみ法律を制定し罰則規定を設けることができます。主権には及ばないが排他性を有しているために、「主権的権利」と呼んで「主権」とは一線を画しているものです。
また、領海とは国家の海岸に沿う基線より外海へ12マイルを越えない範囲で定められた帯状の海域です。上空、海底及びその下を含めた領海は、沿岸国の主権に服する国家領域の一部です。
なお、内水(ないすい)とは、海洋の区分の一つであり、通例、領海の幅を定めるための基線(低潮線)から陸地側の海域を示します。国家は内水に対してもその領土と同様の主権を有し、外国船舶の進入の是非は領有国の裁量に任されています。内水の定め方については国連海洋法条約に規定があります。
|
|
|
バラスト(ばらすと Ballast) |
|
|
船舶の重量を増したり、船体姿勢を安定させる為に積み込む重し、海水等のこと。
|
|
|
引き波(ひきなみ) |
|
|
船が航行時に後ろにできる波、船尾波。
船舶の引き波は、船舶が航行する時、船体が水を押しのけることによって発生します。機関を備えた船だけでなく、帆船、曳航船でも引き波は生じます。蹴波(けりなみ)と言う場合もあります。
引き波の広がり方によって船舶の航行速度をおおまかに知ることもできます。船の中心線に沿って出ているか、どの程度の角度で出ているかということによって、風圧によって船が横方向へスライドしている割合をおおまかに知ることも可能です。
一般に大型船舶の引き波は小型船舶のそれに比べて大きくなります。
大型船の引き波に手漕ぎボートや小型船が不適切な角度で遭遇すると、極端な場合転覆する恐れがあり危険です。
船の速力が大きいと引き波は大きくなる傾向があり、大きな引き波は係留中の船舶を激しく揺さぶりそれを傷めることがあるので、小型のモーターボートであれ、船舶を操縦する時は係留船の付近では十分に速力を落とし極力引き波を立てないのがマナーとされています。
また、怖いことですが地震によって津波が押しよせる前に、海面の水位が一旦下がる現象のことも引き波と言います。
反対は「押し波」あるいは「寄せ波」。
|
|
|
ビルジ(びるじ Bilge) |
|
|
機械等から漏れた水、油等が溜まった汚水、垢のこと。
|
|
|
保持船(ほじせん) |
|
|
海上衝突予防法の規定により、2隻の船舶のうち1隻の船舶が他の船舶の進路を避けなければならない(避航船)場合、もう一方の船舶を「保持船」と呼び、保持船はその針路及び速力を保たなければならないと定められています。
|
|
|
マイル(まいる Nautical mile) |
|
|
海里(マイル、mile)のこと。
mile / nautical mile、陸上の距離としては1マイルは約1,609m(1760ヤード)ですが、海の距離単位としての1海里は1,852mになります。詳しい解説は「海里(かいり)」の項をご参照ください。
|
|
|
領海(りょうかい Territorial sea) |
|
|
国家の海岸に沿う、一定の幅を持った帯状の海域です。上空、海底及びその下を含めた領海は、沿岸国の主権に服する国家領域の一部です。領海の幅は基線より外海へ12マイルを越えない範囲で定めなければなりません。また領海では外国船舶に対し無害通航権が認められています。
なお、ニュースなどでよく耳にする排他的経済水域(通称EEZ)二ついては排他的経済水域の項参照のこと。
|
|
|
六分儀(ろくぶんぎ Sextant) |
|
|
天文航法では太陽や星などの天体の高度を測定しますが、この高度を測るための光学器械を六分儀と言います。円弧状のフレームが約60度分(目盛は120度分)あることから六分儀(Sextant)と呼ばれています。水平に支持して2物標の水平夾角を測定するのにも使用されます。
大型の六分儀は主に天体観測用に使われたのに対し、小型の六分儀は船舶の天測航法用に使用されましたが、近年GPSなどの普及によりあまり利用されなくなってきています。六分儀が航海のシンボルマークとして使われていた時代も長くありました。
|
|
|
ワッチ(わっち Watch) |
|
|
大型船などで行なわれる船橋当直、機関当直のことで、通常1日24時間を3人で分担して当直にあたります。
もともとは、watchの日本語なまりから派生しました。船員言葉で見張り、航海当直のことですがアマチュア無線などでも「傍受」などの意味で使われます。
|
|
|
Anchor(アンカー ) |
|
|
錨(いかり)のこと。アンカー参照のこと。
|
|
|
Chart(チャート ) |
|
|
海図のこと。海図の項参照のこと。
|
|
|
EEZ(イーイーゼット Exclusive Economic Zone) |
|
|
排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき Exclusive Economic Zone 略称EEZ)のこと。
|
|
|
Knot(ノット) |
|
|
速度を表す単位。ノットの項参照のこと。
|
|
|
|
海事法規照会サービス |
|
|
海に関連した法規を掲載しております。
法規は不定期な改正が行なわれることがありますので関係省庁からのプレスリリースもあわせてご確認ください。
なお、このサービスは総務省による「行政手続のオンライン利用の推進」での法令検索へのリンクとしております。
|
|
|

|
|
| | |
|


 海事関連法規の照会サービスと用語集です。
海事関連法規の照会サービスと用語集です。